Vol. 04 / 01











Model : カナイフユキ – Illustrator / Zinester (https://fuyukikanai.tumblr.com)
Photography : ともまつりか
Text : Nozomi Nobody
年明け、フユキさんにとても久しぶりに会った。たぶん2年か3年か、もしかしたらもっとぶりだったかもしれない。ともまつと3人で下北で待ち合わせをして(わたしは遅刻をした)駅の近くのカフェに入った。生い立ちや家族のこと、学生時代からいまに至るまでのあれこれを根掘り葉掘り聞いた。個人的な質問も多かったと思うけれど、フユキさんは嫌な顔ひとつせず、丁寧にいろんな話をしてくれた。ひとしきり話したあと、唐突に「なにが生きづらいですか」と訊いた。フユキさんは長くて濃いまつ毛を伏せて「そうですねぇ…」と少し考えて「普通を求められることですかね」と言った。「〈30代、社会人、男性〉という枠からはみ出すと変なひと扱いされるじゃないですか」
普通という名の見えない枠。明確な境界線はなくともみんながそれとなく共有しているそれ。大学を出て、就職をして、結婚して子供を産み育て家庭を築くーーなど。そういうことでいうと、フユキさんもともまつもわたしも枠からはみ出しまくっている。それぞれイラストや写真や音楽や、主たる活動/仕事をしながら、他の仕事もして収入を得て生活をしている。未婚だし、子供もいない。でもそれがなんだというのだろう。
だけど“枠”なんてなくなればいいと中指を立てる気持ちがある反面、本当はそこに属せない自分に対する罪悪感や劣等感のようなものもずっと拭えずに心の隅にあるように思う。
何年か前、地元の友達との忘年会で久しぶりに会うMと隣の席になった。わたしの地元の友達はほとんどが小中の同級生で、中学卒業からいまに至るまで折に触れてはみんなで集まってはごはんを食べたりお酒を飲んだり、大人になってからは子連れで遊んだりしている。Mは昔から要領が良く、勉強もスポーツもよくできた。明るくてやんちゃで、よく気がつき面倒見が良い、つまりとてもいいやつで、日本の大学事情に詳しくないわたしでもわかるくらい有名な大学を出て、いまはいわゆる大企業に勤める二児の父だ。その日は久しぶりに10人ほどの大人数が集まり、みんなそれぞれに飲みそれぞれに楽しんでいたので、わたしとMはなんとなくふたりで話す格好になった。ちょくちょく顔を合わせてはいたものの、ゆっくり向き合って話す機会は考えてみれば滅多になかったなと思いながらワインをあおっていると思いがけないことを言われた。
「俺はちゃんと社会っていう枠の中で歯車として働いて家庭も持って生活してるけど、お前はその外にいてさ、このままだったら孤独死する可能性だってあるわけじゃん。しかもこれからどんどん市場価値だって下がるんだから早く相手見つけて結婚して枠の中に収まれよ」
通りがかりのひとにいきなり顔面を殴られたような衝撃だった。驚きのあまりなにも言えなかった。ひどく混乱した。
苦しい時期だった。音楽も生活も、なにひとつ思うように行かず、自分がなにをしているのか、なにがしたいのか、わからなくなっていた。家にひとりでいても、道を歩いていても、電車の中でも、急に涙が止まらなくなることが度々あり、あぁこれはいよいよ危ないかもしれないと自分で感じながらだけどどうすることも出来ず日々をどうにかやり過ごして、そうしてやっと生き延び迎えた年末だった。彼の言葉は無防備なわたしの心をさくさくと、フォークでフルーツを刺すように、ことも無げに突いた。テーブルを挟んだ向かい側の席では、昔からよく見知った顔達が楽しそうにお酒を飲み会話に花を咲かせている。わたしはどこかでなにかを間違えたんだろうか。自分の存在を心から惨めに、情けなく思った。ぽろぽろと溢れてくる涙を止めることができないまま、やっとの想いで声を絞り出した。「わたしがもし孤独死したら、そういう人生だったんだなって思うだけだよ」
普通。不思議な言葉だなと思う。誰が決めるんだろう。その枠からはみ出るのはそんなにいけないことなんだろうか。はみ出たひとたちは、“わたしたち”は、いったいどこに存在していることになるんだろうか。
例えば多様な働き方。例えば多様な出生。例えば多様な性。彼の言った“社会”と呼ばれるものは、その枠は、これら全てを丸ごと包括するものであるべきではないか。全部ひっくるめて社会、そのすべてが当たり前で“普通”であるべきではないか。
いまでもときどき、あのときMになんと言うべきだったのかと考える。もしいま彼に同じことを言われたら、わたしはなにを言えるだろう。きっとまた言葉に詰まってしまうような気がする。正直Mに対峙する勇気も自信もいまはまだない。だけど、と思う。わたしはたぶん変われない。わたしはわたしでしかあれない。彼のいう普通の社会の枠の中に自分を押し込めて当てはめることは、それはやっぱりわたしの人生ではないのだろうと思う。そういうのって生まれ持った性質というか性分というか、言うなれば“さだめ”のようなもので、どうしようもないことなのだ。だからわたしはわたしを生きるしかない。わたしはわたしを生きて、その末にちゃんと自分自分も自分の人生も愛して、「こういう生き方もあるんだよ」「けっこう悪くないよ」と身をもって示し表現していくこと。それがわたしのMに対する責任のような気が、いまは勝手にしている。
いつかもっと歳をとったときにまた並んで座って、お酒をちびちび飲みながら「あぁこんな風になったね」とお互いの姿を見て笑い合えたらいいなと、思う。そしてそのためにも、わたしはますます、もっともっとまっすぐに生きなくては、と思うのだった。
Vol. 04 / 01
Vol. 04 / 02
Vol. 04 / 03
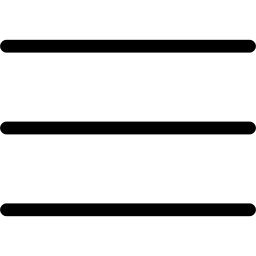

![みちわたるしんたい[8通目]みんなでもひとりでも](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/11/michiwataru_08.jpg)

![みちわたるしんたい[7通目]愛すべき食いしんぼう](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/09/7_1.jpg)

