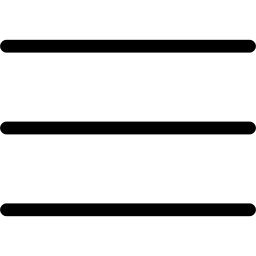
でもあの瞬間、なにをどう選択しあるいはしなくてもいまここにいるわたし以外にはあり得ようがない、あるべくしてなのかなるべくしてなのか、何がどうしてなのかそれはわからないけれど、でも「これでしかあり得ない」という考えが唐突に胸の中に浮かんできたのだった。
とどのつまり美味しいものを美味しく食べられたらそれでひとまずは幸せ、ということなのかもしれません。
「女性であるわたしたちが表現していることが自ずとそこに繋がっていくっていうか、それ自体が希望だし、意識せずとも力になってると思う」
わたしは、いつだってどこにだって、行けるんだよな、本当は、と思う、そしてこの身体を引き止めているもののことを思う。
祖母が焼いてくれたのにとてもよく似た豆餅も入っていて、わたしはそれを懐かしい気持ちでいただいて、すぐそばにはすやすや眠る産まれたばかりの小さな命があり、あぁ繋がっている、巡っている、とひとり感慨深い気持ちになりました。
「自分だけしか知らない、ちいさな違和感。見たくないこと、見せたくないこと。きっとそこには何かが宿っている」
いつもきっとどこかに帰る場所がある、ということだけは、ふわふわ漂うわたしの胸にちいさく灯りをともすのです。
どんなに喧嘩をして相手を憎らしく思っていても、同じテーブルで同じ美味しいものを食べていると人間って怒った気持ちのままではいられないのですよね。
わたしもカツ丼、もといとんかつ、もといあげものが大好きです。でも長かったひとり暮らしの間には殆ど作りませんでした。小さい頃はあげもの作りのお手伝いが大好きだったのに。
勇気を出して自分の声で歌ってみてよかった、と思う。と同時に、ふたりがわたしを歌わせてくれたのだな、とも思う。

![みちわたるしんたい[8通目]みんなでもひとりでも](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/11/michiwataru_08.jpg)

![みちわたるしんたい[7通目]愛すべき食いしんぼう](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/09/7_1.jpg)




![みちわたるしんたい[5通目]たべること、かえるところ](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/01/michiwataru_05.jpg)
![みちわたるしんたい[4通目]天ぷら家族](https://unbared.net/wp-content/uploads/2021/12/michiwataru_04.jpg)
![みちわたるしんたい[3通目]家内あげもの分業制](https://unbared.net/wp-content/uploads/2021/11/3.jpg)
