そこにあった彼女たちの痛みのことを|『ひとり』(キム・スム著、岡裕美訳)

Text : Nozomi Nobody
「これは歳月が流れ、生存されている旧日本軍慰安婦の被害者が、ただひとりになったある日からはじまる物語です」(本文冒頭)
「慰安婦」についてわたしが知っていたことと言えば、そう呼ばれる女性たちがかつていたこと、彼女たちは軍人の相手をさせられ恐ろしい目に遭っていたらしいということ、最近ではあいちトリエンナーレにおける平和の少女像の展示を巡り紆余曲折があり、様々な議論が飛び交っていたことくらいだった。つまり、ほとんどなにも知らなかった。『ひとり』を読み終え、この壮絶な物語を前にして自分の無知と無関心を恥じた。そしてこの本に出逢えて良かったと、ほとんど安堵するような気持ちになった。
『ひとり』は、旧日本軍の慰安婦として十代のほとんどを満洲の慰安所で過ごした女性の一生を描いた小説だ。小説の形をとってはいるが、筆者キム・スム氏が「手に入る限りの資料を集め」(本書訳者あとがき)拾い上げた被害者たちの無数の証言を繋ぎ合わせ、そうして編み上げた、ほとんどノンフィクションといってもいい作品だ。事実、主人公「彼女」の記憶や感情の仔細な描写は、そのひとつひとつがリアルな痛みを伴ってわたしの中に流れ込んできた。こんなに痛い読みものは初めてだった。それでもわたしはページをめくる手を止めることができなかった。それどころか、気づけば次へ次へと、なにかに急かされるように夢中で読み進めていた。
満洲という単語を目にして真っ先に思い浮かんだのが父方の祖母の存在だった。祖母は去年の春に亡くなった。長く入退院を繰り返しており、亡くなる少し前からは施設に入っていた。長野にいた彼女に会うのは年に一度か二度がせいぜいだったが、ときどき両親について顔を見に行っていた。
いま思えば、あれがわたしが彼女に会った最後だったのではないか。高速道路を降り、生命力のかたまりのようなあおさを湛えた田畑のそよぐ道を抜け、その施設を訪ねた。あの日は、両親と姉とわたしの4人だった。とてもよく晴れた日だった。
個室のベッドに横たわる祖母の手は、赤黒い血管が浮き上がり、ほとんど骨と皮だけのようになっていた。父は大きな声でゆっくりと彼女に語りかけたけれど、聴こえているのかも、わたしたちが誰だかわかっているのかも、もう判断がつかなかった。それでもなんとなく父の方に向けられていた目は少し潤んでいるように見えて、わたしにはそれが切なかった。やがてその目を閉じてうつらうつらしはじめたので、わたしたちはベッドを囲んでしばらく他愛のない話をしていた。すると祖母は突然、本当に突然、歌を歌いはじめたのだった。体が一瞬びくっとするほどの音量と明瞭さで。同じ一節だけをくり返しくり返し歌っていた。一聴してそうとわかる、それは軍歌だった。
体を思うように動かせなくなり、話すこともままならなくなった彼女が一言一句なんのくもりもなくほとんど自動的に歌うことができるほど、身体に染み付いていた軍歌というものの存在。わたしは少なくない衝撃を受けた。
祖母が亡くなってはじめて、わたしは祖母のことをなにも知らないということに気がついた。「田舎のおばあちゃん」と言えば、昔はお味噌やらお漬物やらを手作りして親戚近所に分けて歩き、お盆に親戚が集まれば山のような天ぷらを揚げ、おはぎをこしらえ、わたしたち孫に「食べろ食べろ」とすすめ、お裁縫が上手で、背がとても小さく腰が曲がっていて、わたしたちが乗った車をいつまでも手を振って見送ってくれる、そういう存在だった。祖母が自分の話しをするところなんて聞いたことがなかったし、そもそも話しらしい話しなんてしたことがなかった。
コロナ禍で行われたこじんまりとした彼女の葬儀のあと、こじんまりとした会食の席には見知らぬお婆さんたちが、わたしと姉が並んで座るテーブルの向かいに座っていた。祖母の妹たちだった。
わたしたちは、彼女たちに祖母が満洲に行っていたことをそのときはじめて聞かされた。姉さんは頭を丸刈りにして、男物の服をきて、女だとわからないようにして帰ってきたのだと彼女たちは言った。
旧日本軍の慰安婦は平均16、7歳で、中には11~13歳の少女たちもいたそうだ。幼い彼女たちは、工場の仕事で金を稼げると騙されたり、突然拉致されたりした。ある日突然見知らぬ場所に連れて行かれ、一日に十数人あるいは数十人の軍人の相手をさせられた。ろくな食事も与えられず、ぼろぼろになるまで、ぼろぼろになっても、なお傷つけられ、生き、あるいは死んでいった。1930年から1945年までの間に旧日本軍の慰安婦に動員された女性は20万人に上り、そのうち生還したのは2万人だそうだ(本書「作者の言葉」)。
わたしは彼女たちの痛みを想像した。性器をナイフで切られる痛みを。歩けなくなるほどに腫れ上がった性器の痛みを。死んだ仲間が燃やされるその臭いの中で何人もの軍人の相手をする痛みを。妊娠し、胎児とともに子宮ごと取り出される痛みを。すべての痛みを背負ったまま、誰にも言えずに生き続けるその痛みを。
本を読み進めながら、わたしは祖母が満洲で見たものはなんだったのか、想像せずにはいられなかった。
本書終わりの『訳者あとがき』に、生存する被害者の数が着実に減っている背景とともに「問題の解決はさらに急がれる」とあった。
「問題の解決」とはなんだろう。なにを以って、問題は解決されたと言えるのだろう。償うべき罪はだれが負っているのだろう。当時の日本軍?日本という国?日本国民全員?
先の終戦記念日に「日本人は戦争を被害者として語っている、加害者としての意識が欠如している」というあるひとの指摘を目にした。慰安婦にまつわる教科書の記述さえ書き換えられようとしているいま、韓国で数多くの賞を受賞したこの小説は、日本でこそ広く読まれるべきものではないかと、強く思う。
知らないことをひとつ知るたびに、打ちのめされる。知らなかったという事実に打ちのめされ、知るということの果てしなさに打ちのめされる。知っても知っても知っても、足りる日が来ることはない。途方もない気持ちになる。
それでもわたしは知りたいと願う。誰にも知られず死んでいった彼女たちの痛みを。生き続けた彼女たちの痛みを。いまはもう知る術もない、祖母が感じていたであろう痛みを。
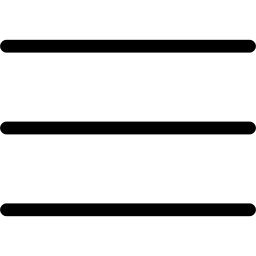

![みちわたるしんたい[8通目]みんなでもひとりでも](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/11/michiwataru_08.jpg)

![みちわたるしんたい[7通目]愛すべき食いしんぼう](https://unbared.net/wp-content/uploads/2022/09/7_1.jpg)

